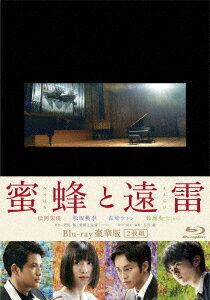登壇者:高橋さやか(『遠い山なみの光』衣裳担当)、小川久美子(『国宝』衣裳担当)
『遠い山なみの光』(9月5日公開)のトークイベントが8月28日(木)、東京・月島のブロードメディア・スタジオ試写室で行われ、本作の衣裳を担当した高橋さやか氏と『国宝』などの衣裳を担当した小川久美子氏が出席した。
ノーベル文学賞受賞作家カズオ・イシグロの傑作「遠い山なみの光」を、日本アカデミー賞受賞監督の石川慶氏が実写映画化した本作。1950年代の長崎と、1980年代のイギリスを生きる3人の女たちの知られざる真実に涙溢れる、感動のヒューマン・ミステリーとなっている。
同イベントには、本作をはじめ、『蜜蜂と遠雷』(2019年)、『ある男』(2022年)などこれまで数々の石川 慶監督作品の衣裳を担当してきたスタイリストの高橋氏、そして邦画実写映画としては歴代3位という歴史的ロングヒットを記録し、来年の米国アカデミー賞🄬国際長編映画賞の日本代表に選ばれたというニュースが飛び込んできたばかりの『国宝』の衣裳を手がけた小川氏が出席。『遠い山なみの光』では1950年代の長崎と1980年代のイギリスを舞台に悦子(広瀬すず)と佐知子(二階堂ふみ)という対照的な2人の女性を、『国宝』では1960年代から平成にかけての時代の変遷とともに喜久雄(吉沢 亮)と俊介(横浜流星)という生まれも育ちも異なる2人の青年を、それぞれ衣裳を通じてスクリーン上に再現してきた2人が、作品や衣装に込めた思いや工夫を語った。
本作を“衣装”という観点でどのように見たか尋ねられた小川氏は「衣装の仕事をやっている人は、みんなやりなくなるような作品だなと思いました」と言い、「イギリスと長崎で衣装の使い方を分けていて、イギリスではリアルさのある衣装ですが、長崎は想像と記憶の世界で、もしかしたら嘘かもしれないと思わせるような作り方になっている。そこがすごく面白いと思いました」と感嘆した。
これを受け、高橋氏は「(小川氏の指摘が)本髄というか(笑)、イギリス・パートで感じるざらつきとか湿度と、私が担当した長崎パートの戦後の描写は完全にタッチが違います。もちろん意識して作ったんですけれど、あらゆる人が(過去を)振り返ったときの記憶を美化するようなことを、衣装でも誇張して表現した部分がありました」と打ち明け、「とはいえ、こんなにはっきりと指摘されると、ちゃんと受け取ってもらえたんだなと思えてよかったです(笑)」とにっこり。
加えて、高橋氏は「美術なども、“この柱はもうちょっと汚れているんじゃないか”とか、“ふすま紙はもうちょっと日焼けしていても良いんじゃないか”と思われると思うんですけど、なるべくエイジングを堪えて。悦子が思い出す当時の記憶としてふわっとさせていたので、それを感じていただけたら、もしかしたらこの映画自体が伝えたいことの半分くらいは伝わっているんじゃないかと思います」と語った。
また、悦子と佐知子の女性像の作り方について高橋氏は「悦子に関しては、長崎の街で普通に育って生活していたということが分かりやすいように、ノーマルにと言ったら変ですけど、そのような形で作らせていただいたんです。長崎という土地柄も意識して、異国情緒あふれる街で育ったというところを、ブラウスのタックだったり、素材の選び方に少しだけ投影したくらいで、あとはよくいる女性というイメージを超えない範疇で作らせていただきました」と明かし、「佐知子に関しては街で目立つ女性、はっきりと“あの人はこの街の人ではないよね”とわかるような装いが必要ですし、彼女のバックグラウンドが衣装からも伝わるような装いにしなきゃなということで、いろいろ考えて作りました」とこだわりを明かした。
加えて、高橋氏は「この映画全体的に言えますが、決めつけて作ってしまうと読み取ってほしいことと違う取られ方をしてしまうので、ぼかしておきたい部分を残しつつ、佐知子に関しては最初に監督から『ちょっと派手めに』という話もいただいて。そのまま佐知子を作ってしまうと完全に商売的なことを匂わせすぎて、本来彼女が持っていた気品とか、生い立ちとか、生活とかが全部なかったことにしてしまうような気がしたので、佐知子に関しては気品とかヨーロピアンなものを取り入れて、よりファッショナブルに作ったという経緯があります」と打ち明けた。
一方、『国宝』では喜久雄と俊介の衣装をどのように作ったか尋ねられた小川氏は「もちろん色彩でイメージをある程度決めていったんですけど、俊介は育ちがいいお坊ちゃんで、やや保守的な格好。一方、喜久雄はその時代のモードというか、ちょっととんがった人たちが好みそうなデザインにしています」と紹介し、『国宝』の衣装を見た感想について高橋氏は「キャラ分けが分かりやすく、同じものを目指している2人の、流れている血もそうですし、人となりも全部衣装から匂ってきました。幼少期など年齢の幅もあって、“これくらいの歳のときはこういう格好をするんだよね”というのが分かりやすく、それがまた立場の違いを表しているなと見ていました。面白かったです」と目を輝かせた。
さらに、本作でどのくらいの衣装を(既製品ではなく)イチから製作したのか聞かれた高橋氏は「悦子、佐知子は8〜9割は作っています」と告白。「普段も好ましいものがなければ年代に関わらず作るんですけど、物語の舞台となる戦後の1950年代は洋裁がブームだったということもあって、すごくオシャレはしたいのに、憧れる服を買うことはできないし、そもそも売ってもいない。だけど装苑さんといった当時の雑誌で展開されている作図や絵を真似して作っていた方が多かったので、今回はリアルに作ったほうが深みが出ていいんじゃないかなと思って作らせていただきました」と明かした。
一方、『国宝』の衣装製作について小川氏は「ないものはすべて作っていきました。現代モノって意外と(既製品で)思ったものがあることもありますが、例えば“形はいいんだけど色がね”とか、そういうこともあるので結構作りますね」といい、製作のプロセスについては「私の場合はまずデザイン画とイメージ画を描いて、そのイメージに似たものがあれば既製品で、なければ作るって感じです」とコメント。現代モノの作品で衣装のイメージが湧かない際は街に出るそうで「街に出ると“これだ”ってこともあります。服が呼ぶんですよね」とエピソードを明かすと、高橋氏も「全く同じです」と共感。
一方、衣装製作のプロセスについて高橋氏は「リアルに隣にいる人を作らないといけないときは、大量生産の洋服を組み合わせたほうが馴染むこともあります。役や場合によるんですけど、最初に(原作や脚本を)読んだときのイメージを絶対になくさないようにして、そこからリサーチと勉強をして、プラス演者が誰になったか。そこで足したり引いたりしながら、最終的に形になる感じですね」と説明し、「やっぱりお勉強することが大事ですね。毎度、テーマや時代もそうですけど、いろいろ勉強をしてパーツが揃うって感じがします」と言葉に力を込めた。
加えて2人は、作品の見せ場がどこかを考えて衣装を決める場合もあるそうで、本作の山場はどのシーンか聞かれた高橋氏は「稲佐山かなと思っていたんですけど、演出的には後半の悦子が少しずつ変化をしていって、映像全体から違和感が漂うところが山場になるのかなと思います」と言い、『国宝』の山場のシーンについて小川氏は「絶対に屋上の踊りの場面は残ると思いました。思った通りの画でしたけど、襦袢なので赤にしようというのはありました。あとは舞台で1人、上を見ているシーンは、なんでもないグレーのスーツなんですけど、だんだん削ぎ落としていくところにポツンといるというイメージを残したかったです」と明かした。
また、本作の衣装の色彩について高橋氏は「佐知子は会うたびに違う印象を受けるような女性にしたくて、その中に上品な色があったり、分かりやすくはっきりとしたパッション・カラーを入れたりして、洋服の着こなしも長崎の人たちからは浮くような感じにしたいと思って作っていたんですが、悦子は対極にあるんです。異国情緒感とか長崎とかこの作品ならではの雰囲気を足していった作り方をしていたので、その差は出ていたかなと思います」と語り、稲佐山のシーンが話題に上ると、佐知子のピンクの衣装が先に決まっていた中、悦子の衣装をどうしようか悩んだそうで「いろんな候補があって、実は薄いオレンジなんですけど、見た方に(佐知子と同じ)『ピンク』と言われるので、もしかしたら徐々に似てきている2人を感じながら見てくださった方がそのように思うのかなと思いました」と分析した。
そして、戦後当時の装苑を見た感想について小川氏は「この時代の女性はもんぺに飽き飽きしていて、一日も早くかわいい服を着たいと思っていたと思うんです。実際には戦前から戦後の日本は華やかな色の時代だったので、割と抵抗なく、飢えていた若い女性たちはもう一度そういうものを着たいと思っていたんだと思います」と紹介し、「今までの日本の映画は(衣装が)シックなんですけど、実際にはもっと色があったんじゃないかなと思います」とコメント。
これを受け、高橋氏は「今回の作業は、モノクロの写真や映画を見て“いったい何色を写してこの濃淡になっているんだろう”という解析から始めて、改めて巨匠たちが作る映画や誌面もたくさん見たんですけど、イラストになっているものを見ると“こんなに色があるんだ”と、派手さに驚きました」と目を丸くし、「それ(戦後を描いた過去の作品)を史実だと思って見てしまうと間違えてしまうんだなと、リサーチする中で思ったので、一回自分の中でリセットして、地味に作りすぎないように取り組みました」と打ち明けた。
最後に、映画における衣装の役割について聞かれると、小川氏は「映画はすべて作りものの世界で、いくらリアルに見えても実は作りもので、話の中のキャラクターの性格も映画を見ていく中で感じていくことだと思います。そういう意味で(衣装は)“作りもの”と“感じさせたいもの”を誘導していくものだと思うんですね。画面で黒いところにいるのと、白いところにいるのでは、同じ衣装でも受ける印象が違うように、画面の中でどう成立するかとか、考えることが山ほどあって、その中でこれにしようと考えています」と言葉に力を込め、高橋氏は「背景説明ですかね。今回の原作者にちなんで言うと、信じすぎてはいけない背景説明(笑)。そのまま受け取っていただきたいこともあるけど、そこに全然違った意味が含まれていることもあると思うので、背景説明かなと思います」と表現した。
公開表記
配給:ギャガ
9月5日(金) TOHOシネマズ 日比谷 他 全国ロードショー
(オフィシャル素材提供)