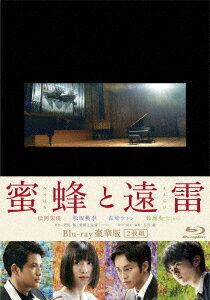登壇者:石川 慶監督×三宅香帆(書評家)
1989年にイギリス最高の文学賞であるブッカー賞、2017年にノーベル文学賞を受賞し、二つの世紀を代表する小説家となったカズオ・イシグロの鮮烈な長編デビュー作「遠い山なみの光」を、『ある男』(22)で第46回日本アカデミー賞最優秀作品賞含む最多8部門受賞を果たした石川慶監督が映画化した『遠い山なみの光』は大ヒット全国公開中。
語りの名手イシグロの作品を、どのように映像にしたのか?
公開されたばかりの本作について、石川 慶監督と、原作小説の解説を手がけた三宅香帆氏が語り尽くす!
映画を観た方はもちろん、これから観る方にとっても、作品の理解が一層深まる特別な時間となった。

イベント冒頭、映画の感想を求められた三宅は「本当に素晴らしい映画で。びっくりしたというのが一番の感想」と切り出すと、「もともとカズオ・イシグロ自体がすごく好きな作家でした。ただ原作小説はデビュー作ということもあって、割と分かりづらいところがある小説だとも思っていたんですが、映画ではそうしたところもいろんなもので補っていて。ひとつの作品として、むしろ映画ではじめて完成形を見たような感じがしました」と称賛。「現実の問題と、歴史的な映像が入り込んでいたことで、小説のテーマが、ドキュメンタリー的にも社会的にもよりよく分かるような構成になっていたのがすばらしくて。あと何より映像が美しくて、そこにもグッときました」と原作ファンならではの熱い感想を付け加えた。

一方、本作が正式出品されたトロント国際映画祭から戻ってきたばかりだという石川監督も「トロントから戻ったばかりなので、まだ日本での感想は把握していないけど、身近なところから熱い感想をいただいている」と続けた。
原作は40年以上前に書かれたカズオ・イシグロのデビュー作。この小説を現代の日本で映画化するにあたり、カズオ・イシグロからの提案の一つとしてあがったのが、小説を書いた直後に盛り上がっていた「グリーナムコモン」という女性たちによる反核運動だったという。
石川監督「いろいろ調べてみると、反核というだけでなく、女性たちだけの運動というのが面白いなと思いました。そこから環境問題だったり、今に繋がってくるものの萌芽がその運動にはあって。今の世代に届くんじゃないかと思った」。

三宅「面白いですね。この作品はフェミニズムみたいな視点から見ても、ちょっと複雑な話だなと思っていて。パッと見たら悦子と佐知子って保守的な女性と進歩的な女性に見えるんだけど、進歩的に見える中にも不安定さがあったりして。特に戦後で混乱した時期だということもあって、社会的に見るとやはり女性がまだまだ危うい立場の中で強がっているみたいなところがある。そこにイギリスに渡った悦子の、娘との葛藤みたいな話もある。そうしたものが何段階もある複雑な話なので、そこに反核でありながら、ある意味フェミニズム的な運動でもあるグリーナムコモンの運動を持ってくるというのは、女性たちが子どものためにいろんなものを守る、という意味もあって。二重三重にも受け取ることができるなと思いました」。

原作に描かれていた表現が時代と共に伝わらなくなってきた状況を受け、今の時代の人々に伝わりやすくする、ということについて、石川監督は「その中で一番本当に背中を押してくれたのがカズオさんご本人でした。カズオさん自身が自分の物語をどういうふうに後世に伝わってほしいかと考えたときに、一字一句変えずに保存してほしいとは全く思わない。そんなことよりも、原始から伝言ゲームに近い形で、その人の解釈が加わって次の人に伝わって。物語のように変容して自分が最初に書いているものとは違う形で残るかもしれないけど、それが後世の人たちに記憶してほしいやり方なのだ、と。だから、映画をつくるときにもこれはあなたの解釈でやってくれて、尊重しないで作ってくれるぐらいが一番いいとおっしゃってくださって。一番難しかったですけど、やっぱりカズオさんだからこそできた映画かなと思いました」。

そんなイシグロと話しているなかで解釈が広がったのが三浦友和演じる緒方という役だった。石川監督は「カズオさんは、緒方というのは『遠い山なみの光』の中では面白いキャラクターだと思ったんだけど、どこかで消化不良なところがあって、『日の名残り』(でアンソニー・ホプキンスが演じた主人公)のスティーブンスになったんだ、とおっしゃっていて。自分の中の妄想がめちゃくちゃ広がりました(笑)」。

「そう思うと緒方と悦子にも『日の名残り』の関係性をちょっと感じる。脚本段階ではもうちょっと悦子は緒方に憧れ、あるいは初恋に近いものがあったんじゃないかとか……(結果、明確には描いていないが)どこかにそういうものが感じ取られてもいいかなと自分では思っていて。そこで大事になってくるのがキャスティングなんですよね。今回カメラマンがポーランド人だったんですけど、緒方を演じる三浦さんをパッと見て『すごくハンサムだな。ひょっとしてこれってこういうことなの?』と言っていましたね(笑)」と語る。

また、悦子の夫・二郎(松下洸平)のキャスティングについてきくと、「やはりカズオ・イシグロ作品で一番面白いなと思うのが、その辺がグレーなところ。たとえば二郎は新しいものに向かっているけれども、どこかで家父長制にも囚われているところがあって。それはカズオさんのどの作品にも、どのキャラクターにもあるというのが、大事にしないといけない部分なんだろうなと思いました」それに対し三宅は「その辺りが映画を観ただけでパッと伝わってくるのがすごいなと思いました」と感想を述べた。
石川は、本作をつくる際に実際に長崎にもロケハンに行ったと言い、「カズオさんの生家の近くを歩くと、本当に細い道がたくさんあって、ここに悦子や佐知子がいそうだなという感じがしました。ここだからこその物語だなと感じたんです。そのうえで、映画を作るときは全部具体的にしないといけないので、架空の長崎の地図を作ったんですけど、稲佐山があって、駅がここで団地はここかな、佐知子の家はここかな……、とやっていくと、長崎に(原作に出てくるような)川はないよね、って。あ、これカズオさんの頭の中にしか存在しないんだ、となってそれが突破口になりました。そこから、これはカズオさんの頭の中だけじゃなくて悦子が覚えていた長崎なんだ、50年代の長崎を再現しちゃいけないんだ、作らないと原作の長崎にならないんだ、と気づいて、そこから衣装とかもフィクション的なものを入れていったんです」と実際の長崎を歩いて気づいたことを明かす。
三宅も「私も原作の解説を書いた時に気dいたのですが、1950年代の段階ではないはずのタワーが出てきたりして。これは本当に記憶の中の長崎の話なんだなと思って。具体的に何年代って書けないなと思いながら書いたりしたので。本当に“思い出す”というのがカズオ・イシグロ的なテーマだなと思いました。でも“思い出す”風景を映画にするのは難しいと思うんですが、でも映画には確実に思い出している感覚のようなものが出てきているのがすごいなと思いました」と絶賛。

それに対し、石川監督は「記憶の話をつくるときに参考にしたのがアンソニー・ホプキンス主演の『ファーザー』という映画でした。アルツハイマーで物忘れをしていく老人の視点から描いた映画だったと思うんですが、家だと思っていたところが実は病院だったとか、自分の部屋だと思っていたところが実は子どもたちの家だったとか。それが主人公の視点で描かれているので、観ている方もどこにいるのか分からない。こういった“信頼できない語り手”という視点で、本作では長崎を描くときに、観ている人に100%信頼しないでくださいね、というところを意識していました」。
内容を深掘りした密度の濃いトークショーもいよいよ終盤。最後のコメントを求められた三宅は「本当に映画をもう一回、二回ぐらい観返したくなるようなお話ばかりだったので、私としてももう一回観に行きたいなと思いましたし、監督の物語のイメージが細部まで仕切られてるからこそ素晴らしい映画になったんだなとひしひしと感じました」。
石川監督も「三宅さんに導いてもらって楽しくお話しできました。ありがとうございます。映画は公開中ですが、賞味期限の長い映画をという想いでつくっている部分もあるので。ぜひ皆さんの周りの方に勧めていただけると嬉しいなと思います」と締めくくった。
公開表記
配給:ギャガ
大ヒット公開中!
(オフィシャル素材提供)