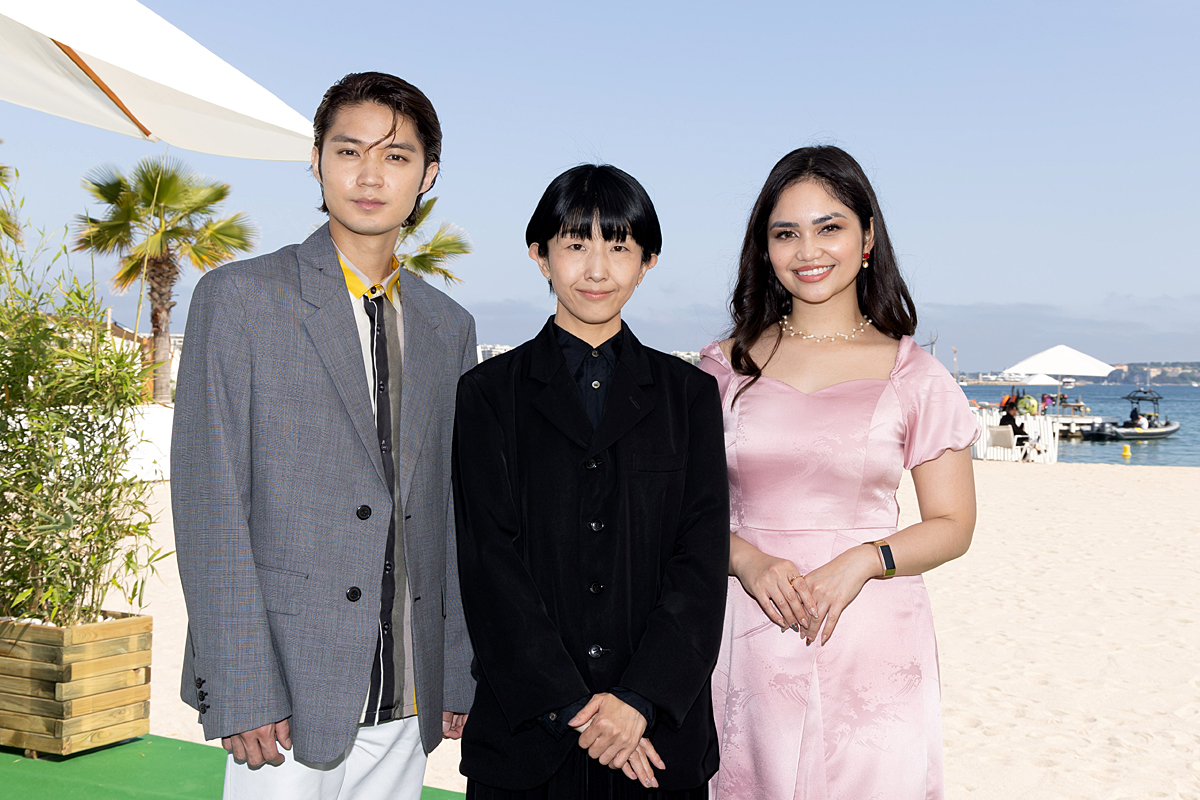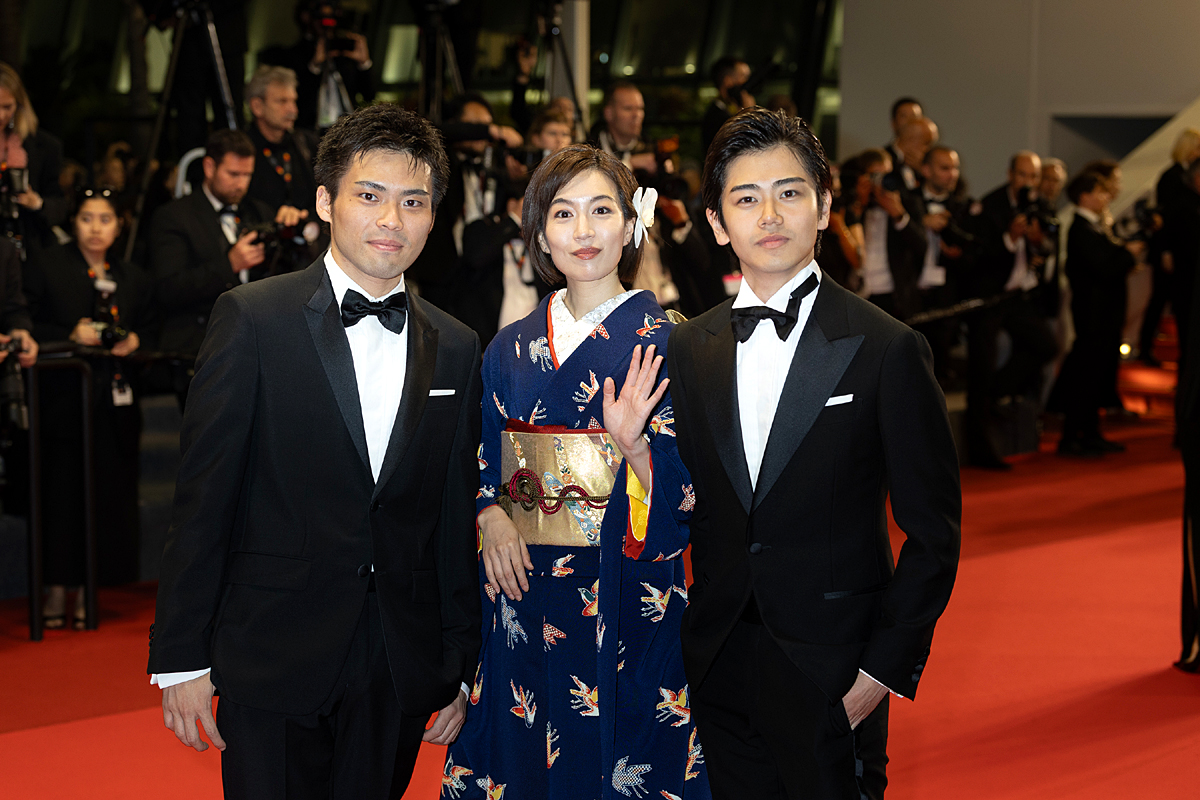登壇者:早川千絵監督、鈴木 唯、石田ひかり、リリー・フランキー
フランス時間5月17日(土)、コンペティション部門での公式上映を無事に終え、約6分間ものスタンディングオベーションで称えられた『ルノワール』(英題:REINOR)。翌日の5月18日(日)には、早川千絵監督をはじめ、主演の鈴木 唯、石田ひかり、リリー・フランキーがフォトコールと公式会見に出席した。本作は、最高賞である「パルム・ドール」を競うコンペティション部門に選出された唯一の日本映画となる。昨日のワールドプレミアを経て、早速海外メディアから「エレガントで思慮深い作品」(Screen Daily)、「ニューカマーである鈴木 唯の演技がまばゆく美しい」(The Hollywood Reporter)などと絶賛の声が上がっている。
晴天に恵まれたカンヌ。真っ青な青空をバックに、変形の白いシャツと黒のパンツという装いに身を包んだ早川千絵監督、大きな白襟が特徴的な紺色のワンピースで可憐な雰囲気の鈴木 唯、淡いグリーンの模様の着物の姿の石田ひかり、セットアップに揃いの黒いハットを装ったリリー・フランキーの4名がフォトコールの場に登場。

昨夜の熱狂そのままに世界各国から集まった大勢のスチールカメラマンやマスコミ陣から、激しいフラッシュを浴び、シャッターが切られた。特に、早川監督と鈴木には「チエ!」「ユイ!」等との呼び声が集まり、飛び交う目線やポーズのリクエストに、2人は笑顔を見せた。また、石田、リリーもリラックスした様子で手を振りながらマスコミの撮影に応じた。







続いて、パレ・デ・フェスティバル・エ・デ・コングレで行われた公式記者会見には、プロデューサーの水野詠子、Jason Gray、Christophe Bruncherも出席した。

本作の制作意図を尋ねられた早川監督は、「私が映画を撮りたいと思い始めたのは、『ルノワール』の主人公・フキと同じぐらいの年頃でした。その時に抱えていた気持ち、感覚をいつか絶対に映画にしたいと長年思ってきました。いつしか、子どもが主役の映画を撮りたいという思いを、今回、実現させることができました」と万感の表情。また、「子ども時代というのは、自分が何を感じているのか、起きているのかをなかなか言語化できない時期だと思うんです。当時、感じていた何か分からなかったものを、大人になって段々と分かってきて、自分は寂しかったんだ、哀しかったんだ、傷ついていたんだという気持ちを描きたいと思いました」と本作に込めた感情を明かした。

続いて、早川監督と現場でどのようなやり取りがあったのかと質問を受けた鈴木は、「早川監督と一緒にフキちゃんの行動や考え方を話し合いました。監督と私は相性が良かったんじゃないかなと思うほど、スポン、スポンとピースがはまっていくような感じでした」と堂々と回答。
早川監督は、「唯ちゃんにはディレクションをしなくても、彼女が自然にそのままのお芝居でやってくれたものがほんとうに素晴らしかった」と絶賛、そして、「彼女が言う通り、私たちはとても相性が良かったです。フキという少女について、私と唯ちゃんは誰よりも彼女のことを理解していたので、撮影の中盤からは何も説明してなくても分かるから大丈夫だという状況になっていました」と振り返った。セリフが少なく、出演者の演技から多くを感じ取る作品であると評したジャーナリストから、キャスティングについて聞かれた早川監督は「フキはキャスティングがとても重要になると考えていたので、見つかるまでとにかく何百人でもオーディションを続けようと臨んだのですが、鈴木 唯ちゃんが一番最初にオーディションに現れた瞬間、“ここにフキが居る”と思い、すぐに決まってしまいました」と衝撃の出逢いだったことを明かした。

今回、三度目のカンヌ国際映画祭の参加となったリリーは、「昨日、レッドカーペットを歩いている時、この映画そのものが出演しているような感覚がありました。映画『ルノワール』が温かく受け入れられ、評価されたことがとても嬉しかったです。皆で楽しくレッドカーペットを歩くことができたのも印象的です。この映画は、特定の国や文化を超えて、誰の心にも響くものがあると思います。登場人物の記憶や、子どもの頃の思い、もしくは後悔や自分自身の感情などいろいろな感覚を呼び起こしてくれます。私自身、この映画の大ファンとして、みんなと共にレッドカーペットを歩けたこと、そして多くの方に観ていただけたことをとても嬉しく思っています」と笑顔を見せ、手ごたえを感じていると振り返った。


海外のメディアから、劇中に“ルノワール”の絵画が登場することについて尋ねられると、「私が子どもの頃に、西洋美術の絵画がとても人気で、あらゆるところでレプリカが売られていました。偽物の絵画なのに、すごくゴージャスで、額縁に入れられていて。劇中にも出てくるイレーヌの少女の絵は、私も憧れて、父親にねだったという思い出があるんです。自分自身の子どもの時代と80年代後半の当時の日本の社会への郷愁もあり、そういった理由であの絵が登場します」と早川監督は理由を明かした。
また、ロケーションについての質問には、「80年代後半の町の面影のある場所を探していたところ、本作の撮影監督を務めている浦田秀穂さんから、ご自身の生まれ故郷である岐阜市を提案してもらいました。実際にロケハンで伺ってみたら、求めていた雰囲気があり、80年代の建物も残っていてとても美しい町並みだったんです。特に魅力的だったのは、長良川が流れていることです。とてもシネマティックでここしかないなと思い、岐阜で撮影することを決めました」と回答。

これは子どもの目線の映画なんだとはっきり意識するわけではないが、気づくとその目線に惹き込まされたというメディアは、カメラのアングルなどこだわった点について質問。カメラと被写体の距離感が重要だと考えたそうで、「被写に対して非常に近い距離ではあるのですが、決して近すぎない絶妙な距離を保つようにしています。また、カメラの奥行きも大切にしました。映像に深みを持たせることで、画面に映るものの意味や重要性が観客に自然と伝わるようにしたかったのです」と早川監督は答え、また、「この作品には説明的な要素があまりないため、観客が感じ取れるリズムも意識しました。私自身が好きな映画のリズムというものがあり、それをベースに構成しています」とこだわりを明かした。
日本のメディアからは、国際共同製作というのがもたらしたメリットについて質問されると、プロデューサーの水野は、「今回の映画は、日本、フランス、シンガポール、フィリピン、インドネシア、カタールと皆さんの協力があって出来上がった作品です。もちろん資金の面での協力もありますが、それよりもクリエイティブな意味で非常に大きな協力関係を得られたと思います」と回答。早川監督の作品をプロデュースすることになった経緯について、水野は、「早川監督がシネフォンダシオン部門で『ナイアガラ』が上映された際に出会ったことがきっかけで、本作を入れて三度目のコラボレーションをさせていただいております。人間の魅力、在る姿を作り込むのではなく、非常にオーガニックに描き、在るがままに表現されるところに魅力を感じています」と語った。また、ジェイソン(Jason)は「水野さんがおっしゃったように、私たちは長い間一緒に仕事をしてきて、その関係は映画を重ねるごとにより豊かで深いものになっています。私は、早川監督が真の作家主義の映画監督だと信じています。音やビジュアル、演出といった当然の要素だけでなく、ポスターやサウンドトラックなど細部に至るまで、彼女は全てにおいて、こだわり、携わっています。彼女のような、緻密なビジョンを持つ監督と一緒に仕事ができるのは光栄なことです。そして、早川監督の映画を、私たちのすべてのパートナーと共に、同じチームとして世界中の観客に届けられることもまた大きな喜びです」と感謝を述べた。そして、クリストフ(Christophe)は、「以前から、水野さん、ジェイソンさんのことはよく知っていて、一緒に仕事がしたいと思っていました。彼らはクリエイティブなプロデューサーです。そして、日本とヨーロッパの架け橋をつくる能力があります。だから、本作のプロジェクトが効率的な国際共同製作になると確信していました」と語り、参加した理由を語った。

公開表記
製作幹事・配給:ハピネットファントム・スタジオ
6月20日(金)より全国ロードショー
(オフィシャル素材提供)