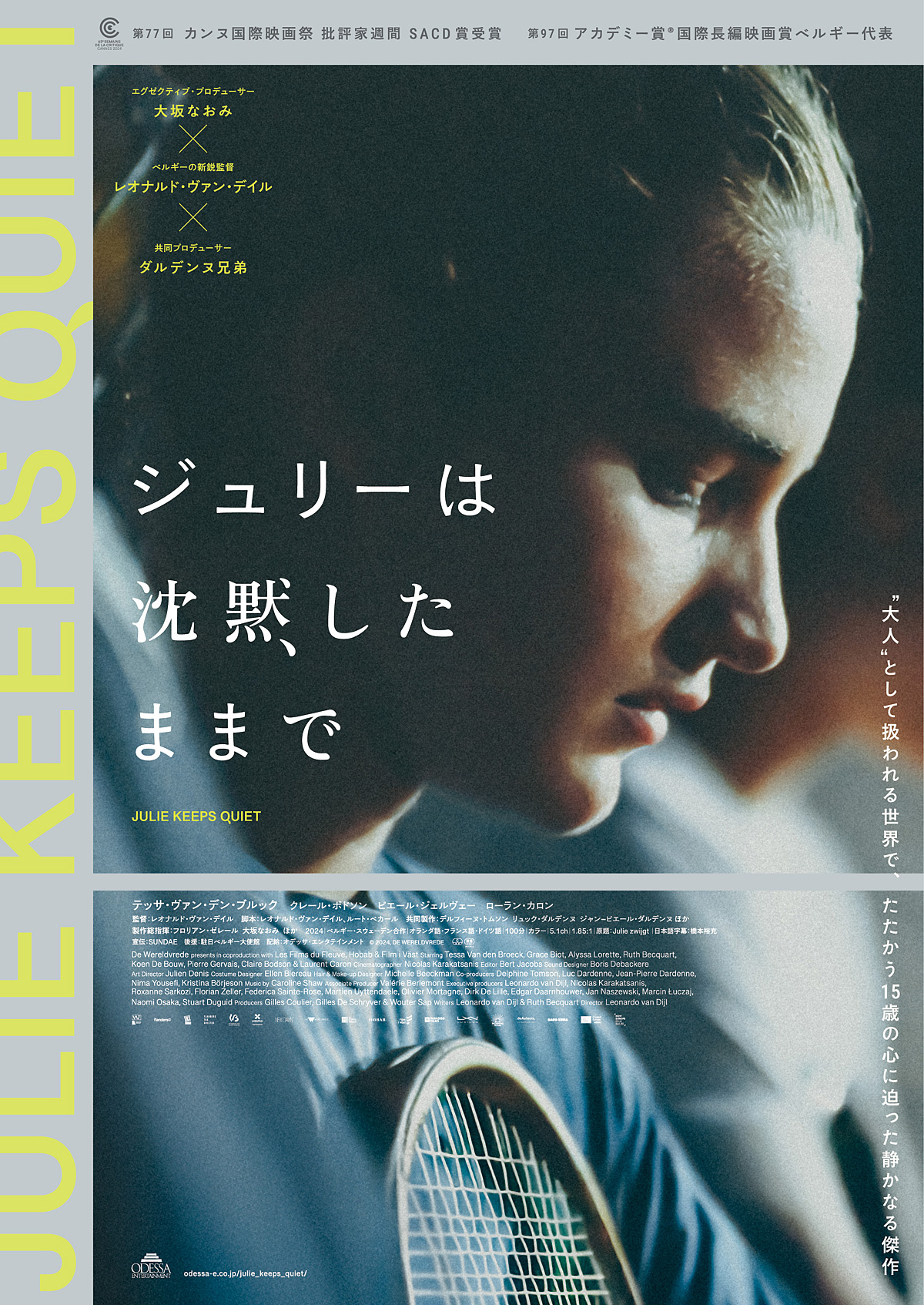登壇者:石山蓮華(電線愛好家・文筆家・俳優)、野中モモ(ライター・翻訳者)
史上最年少のマン・ブッカー賞候補となった作家デイジー・ジョンソンによる「九月と七月の姉妹」(原題:Sisters)に着想を得て制作、2024年カンヌ国際映画祭でのプレミア上映以降も各国映画祭で大絶賛! フランス人俳優として世界的に活躍するアリアン・ラベドがメガホンをとった長編デビュー作『九月と七月の姉妹』(9/5公開)。
9月7日(日)、電線愛好家・文筆家・俳優の石山蓮華と、ライター・翻訳者の野中モモによる公開記念トークが開催された。
生まれたのはわずか10ヵ月違い、いつも一心同体のセプテンバーとジュライ。我の強い姉は妹を支配し、内気な妹はそれを受け入れ、互いのほかに誰も必要としないほど強い絆で結ばれている。しかし、二人が通うオックスフォードの学校でのいじめをきっかけに、シングル・マザーのシーラと共にアイルランドの海辺近くにある長年放置された一族の家<セトルハウス>へと引っ越すことになる。新しい生活のなかで、セプテンバーとの関係が不可解なかたちで変化していることに気づきはじめるジュライ。「セプテンバーは言う──」ただの戯れだったはずの命令ゲームは緊張を増していき、外界と隔絶された家の中には不穏な気配が満ちていく……。歪なほどの近しい関係性で繋がった、妹セプテンバーと姉ジュライ<絡み合って、ほどけない>15歳の姉妹のいびつな絆を映し出す、終わらない悪夢のような本作。
鑑賞後の感想について、石山は「昔、私にもまるで姉妹のようなかなり近しい友人がいたので、(映画の姉妹関係が)彼女との関係にリンクする部分があって」と明かす。「時に私はジュライであり、セプテンバーでもあり、その時々で役割がスイッチするようだった」「まるで(当時を)追体験するような鬱陶しさと愛しさ、そして、かけがえのなさのようなものが詰まっていて、いい意味で息が詰まる。面白く観ました」と振り返る。
続いて野中は「息苦しさがあってもどこにも行けない10代の感覚を映像と音を活かして形にしていた」と称賛。「若い女の子は、映画の中ではとても綺麗に描かれることが多い中、本作では<そうじゃないリアリティ>を形にしようという意欲をすごく感じました」とラベド監督のオリジナリティにも言及。「すごく特殊な関係に見えても、これによく似た状況がどこにでもありそうに思えるところが現代的だなと思いました」と続け、石山は「とても身近というか、なんだか自分を見ているような感覚がありました」と応じた。

また、石山は劇中でセプテンバーが自身の体毛を揶揄われているシーンを挙げ、最近の自身のエピソードとして、俳優業で役柄に合わせて自身の体毛を剃った時のことを述懐。「いつか体毛を生やしたままの役が来たらいいなと思っているので、普段は脱毛していないんです。でも、やはり日本だと普通に脇毛が生えている女性の役はなかなかない。たとえば『全裸監督』には脇毛のある女性は登場するが、それは脇毛をアイコンにしていたポルノ女優という役柄で、ただの体毛ではないように思う」という現実を示し、野中も「手を加えているのがスタンダードというのは、冷静に考えるととても変」と同意。自身が5年ほど住んでいたイギリスでの経験として「体毛があっても、ノーブラでも、日本ほどは気にされなかったかも」と振り返る。そして「時間とお金と労力が必要で、さらに肌がカミソリ負けするとか、人によっては健康が損なわれる危険性まであるのに、(毛を剃っていることが)“当然のマナー”とされていることのおかしさを考えてみていただきたいなと思いますね」と、当たり前とされていることを自身の頭で冷静に考えてみることの必要性も語った。
また、本作を見て『九月姫とウグイス』(サマセット・モーム/岩波の子どもの本)という児童書を想起したという野中。心優しい末っ子の<九月姫>と、親から適当にあしらわれて育ち、歪んだ性格になってしまった8人の姉たちが登場する物語だが、本作の10ヵ月違いで生まれてきた姉妹(=出産直後の父と母の同意のない性交渉を示唆している)という設定について、「『九月姫とウグイス』は、望まれずに生まれてきてしまった娘たちのお話なので、ここから着想を得たのかも?と、この本のことを思い出しました」と話す。
それを受けて、「母親がケアに向いてなさそうなところも印象的だった。私自身も人をケアするのに向いていないだろうと、よく感じるので」と石山が述べると、野中は劇中の<父親不在>について触れながら「ケアの得意ではない母親がケアをしている、というのはすごくありふれた話だと思う」と述べた。
そして二人のトークは、自分の子どもをモデルに自身の作品を作る母親のキャラクターを通して<身近な人を題材に作品を作る難しさ>についても発展。「身近な人のプライバシーや権利をどうするか。大人になってから、本当は嫌だったと子どもが親を告発するケースもある」とSNSを中心としたメディアが発達した現代ならではの事情にも触れ、「家庭内では子どもは絶対的に弱い立場だから、基本的にはやめたほうがいいと思う。とはいえ、親がどれだけ大変な思いをしているかということが、あまり世間には知られずに来たから、特に母親に負担を強いる社会になってしまっているのかなとも思うんです。何かを公表することは危険を伴うけれど、黙っていると無いことにされてしまう。そういう問題に、みんなが直面しているのかな」と続けた。
一方、ラジオ・パーソナリティや文筆家として活動する石山は、「今、異性のパートナーと暮らしていて、私がだらしなさすぎてパートナーに怒られた話もラジオで話したりします。そういう時は、必ず彼に許可を取った上で話す」、さらに「(冒頭で触れた)昔の友人についてもエッセイに書いたことがあったが、公に出す前に許可をとっていた」と自身の経験を振り返りつつ、しかし「子どもの頃は互いに自分のダブル(分身)のように近かった人であっても、関係性が変わった後に(過去に取った許諾のままで)掲載し続けるのは良くないんじゃないかと思ったので、掲載先に伝えて少し内容を変えさせていただいたこともありましたね」と、現代の多様なメディア環境との向き合い方の難しさも語った。

本作はラストまで見届けると分かる仕掛けがあるが、すでに2回鑑賞した石山は、『関心領域』の音響監督として話題を呼んだジョニー・バーンが手がけた緻密な音の設計にも触れつつ、「映画って繰り返して観ると観え方が変わる。2回観る意味を感じた」と語り、最後に野中は「最近、女性監督の映画がいろいろ公開されている中の1本として重要作だと思う」と締め括った。
公開表記
配給:SUNDAE
渋谷ホワイトシネクイント、ヒューマントラストシネマ有楽町、新宿シネマカリテほか公開中
(オフィシャル素材提供)