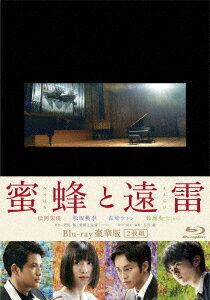Courtesy Vue Lumière
登壇者:吉田 羊、カミラ・アイコ、カズオ・イシグロ、石川 慶監督、石黒裕之(プロデューサー)
カズオ・イシグロ原作、石川 慶監督による映画『遠い山なみの光』が、第69回ロンドン映画祭(BFI London Film Festival 2025/10月8日〜19日開催)のStrands部門へ正式出品した。ロンドン映画祭は、英国映画協会(BFI)が主催するイギリス最大級の映画祭で、1957年に創設。毎年秋にロンドン各地で開催され、世界各国から選ばれた最新の話題作や独立系作品、ドキュメンタリーなど幅広いジャンルを上映し、新進気鋭の才能から巨匠監督まで多彩な作品が集まり、観客・批評家・業界関係者が一堂に会する国際的な映画イベントである。
今回『遠い山なみの光』が選出された部門<Strands>の映画は、テーマごとに編成されており、新たな発見を促すとともに、これまでにない観客層にも映画祭を開かれたものとすることを目指している。<Journey>カテゴリは、観客を非日常へと連れ出し、物の見方を変えるような旅や目的地に焦点を当てた作品群が選出され、過去には、三宅 唱監督『ケイコ 目を澄ませて』なども上映されている。
そんなロンドン映画祭に、ノーベル文学賞受賞作家であり、本作の原作者のカズオ・イシグロ、監督を務めた石川 慶、キャストの吉田 羊、そしてカミラ・アイコが登壇! 吉田 羊は松竹梅柄の着物で日本流の祝賀感を出し、帯は映画の中でも印象的な猫の柄を選択。帯留には英国女王をイメージしたクラウンモチーフをあしらうなど、日本とイギリスの架け橋になるようないでたちで、観客からも大きな注目を集めた。

公式上映はカーゾン・メイフェア・シネマのスクリーン1(307席)で開催され、この日のチケットは発売開始と同時に即完売。映画への期待が渦巻く満席の会場の中、上映前の舞台挨拶としてMCから紹介された石川 慶監督が舞台上にあがると観客からは温かい拍手が沸き起こり、監督からカズオ・イシグロ、吉田 羊、カミラ・アイコ、プロデューサーの石黒裕之らが紹介されると、その拍手は一層の盛り上がりを見せていた。
公式上映後には、本編終了と共に盛大な拍手で迎え入れられた石川 慶監督、吉田 羊、カミラ・アイコ、そしてカズオ・イシグロによるQ&Aセッションが開催。
映画化のきっかけを聞かれた石川監督は、日本人にとって「長崎」というのは非常に大きなテーマであること、そしてカズオ・イシグロの原作にあるような「日本の外側であるイギリスからの視点で長崎を語る」という切り口であれば、戦争の実体験のない自分たちの世代でもこのテーマに取り組めると思ったことを説明。
次に、主人公・悦子の娘役を演じたカミラ・アイコが、原作と映画では自身が演じた「ニキ役」が大きく違っていることについて語り、その違いにこそ監督の想いが込められており、ニキの視点は過去の物語を次世代に伝えていくという本作の重要なテーマの大きな役割を担っていると、監督の想いに共鳴した。
MCから「悦子のキャラクターをつかむきっかけになった台詞は?」との質問を受けた吉田は、脚本に一番印象に残った台詞があったのだが、実は本編には使われなかったのだと明かし、場内から笑いが上がる。台詞に関しても、自身の解釈と監督の解釈の間にニュアンスの違いがあったということで、その違いから「悦子」という人物像を作り上げていったという、役作りの秘話を披露した。
カズオ・イシグロは、MCから「石川監督に本作をゆだねた理由は?」と聞かれ、「ヴェネチア映画祭で『ある男』を見たときに、石川監督が信頼できるきちんとした映画人だと確信したので、私は身を引き、全てを彼にゆだねることにした」と、理由を明かす。映画は石川監督の作品になるべきで、原作者が過剰にかかわったり、監督が原作に忠実であろうと意識しすぎると、たいていの映画はうまくいかなくなる、と持論を展開。「物語」というのは、人の手に渡り、年月と共に読者がそれぞれの解釈や感情を加え、時代や観客によって姿を変えていくものだと話し、石川監督が話した「次世代へ伝えていくこと」というテーマへとトークは帰結していった。
Q&Aの後半では、客席からも吉田 羊や石川監督への質問が寄せられ、英語での演技について質問を受けた吉田は、「できるだけ英語で話してみます」と、通訳なしの英語で回答。「日本語のセリフに比べて英語のセリフを覚えるのはとても大変でした。でも、この役を作るうえで一番大切だったのは、彼女が長崎からイギリスに移ってからの30年間の人生を想像することでした」と、流暢な英語で自らの演技や役作りを振り返った。
最後に監督が、「今回の作品は“記憶”についての映画だと思っています。実際の長崎をそのまま再現することが目的ではなく、記憶の中の長崎を描いています。戦後の長崎というと、人々はどうしても原爆の爪痕ばかりを想像しますが、実際には、すでに人々は前に進み始めていて、ファッションを楽しんだり、日常の喜びを取り戻していた。私たちは、そうした姿を描きたかった。そして、それは1950年代の日本映画ではほとんど描かれなかった部分でもあります。だからこそ、それがこの作品づくりの大きなコンセプトのひとつになりました」と、上映後のトークイベントを締めくくり、会場からは改めて大きな拍手が沸き起こった。

Courtesy Vue Lumière
戦後80周年となる 2025年にスクリーンに描かれたこの物語は、終戦間もない長崎という、まだ過去にしきれない「傷跡」と、未来を夢見る圧倒的な「生」のパワーが渦巻いていた時代を生き抜いた女性たちの姿を鮮明に描き出す。先の見えない時代を生きる私たちに前へ進む勇気をくれる、感動のヒューマン・ミステリー。是非、劇場でお楽しみいただきたい。
ロンドン映画祭 公式上映前の舞台挨拶 全文
MC:石川監督、まず映画について一言お話しいただけますか? その後、素晴らしいゲストの皆様をご紹介いただけたらと思います。
石川監督:今夜、私たちの映画をお迎えいただきありがとうございます。それでは、私のチームをご紹介させてください。まず、カズオ・イシグロさん。そして素晴らしい俳優の吉田 羊さんとカミラ・アイコさん。プロデューサーの石黒裕之さんです。
MC:もう少し広いステージが必要かもしれませんが、何とか収まるでしょう。実に豪華な面々です。上映後には石川監督、吉田 羊さん、カズオ・イシグロさん、カミラ・アイコさんが登壇し、作品についてお話をお聞かせくださいます。質問を用意しておいてくださいね。これからご覧になる作品への心構えとして、何か一言ありますか?
石川監督:上映後に戻ってきます。どうぞ、質問がたくさんあればお願いします。
MC:どうもありがとうございました。もう一度拍手をお願いします。
ロンドン映画祭 公式上映後のQ&A 全文
MC:では、早速舞台にお呼びしましょう。石川 慶監督、吉田 羊さん、カミラ・アイコさん、そしてカズオ・イシグロさんです。まずお聞きしたいのは、この小説の重要性についてです。どんなテーマや構成に惹かれて、これを映画化したいと思ったのでしょうか?
石川監督:この小説は何度も映画化されそうになったけれどなかなか前に進めなかった企画です。我々日本人にとって、“長崎”はすごく大きいテーマです。それを自分たちの世代はどう扱えるのかと考えたときに、カズオ・イシグロさんが外からの目で、イギリスからの視点でこの題材を語っていたので、この距離感ならこの題材に取り組めると思いました。特に戦後80年ということもあったので、今回はそういう思いで作りました。
MC:カミラさんにお伺いします。カンヌ上映後のインタビューでカズオ・イシグロさんが、あなたの演じたキャラクターの重要性について話していたのを読みました。彼は、あなたの役は一種の“読者の代理(proxy reader)”のような存在だと言っていたんです。彼女は自由です。まるで物語のように自由。その点について少しお話しいただけますか? また、それもこの役を引き受けるうえで魅力のひとつだったのでしょうか?
カミラ:ええ、まさにそうです。私が一番印象的だったのは、ニキが原作と映画ではまったく違う人物として描かれていることです。映画の中では、彼女はもっと主体的な役割を担う必要があるんです。原作を読んだときは、娘であるニキが帰ってきたことで悦子に自然といろんな思いがよみがえる、そんな受け身の印象を持っていました。でも映画では、それが“世代を超えて共有されていくもの”になっている気がします。それは石川監督の解釈にも大きく関係していて、この物語や過去に起きたことを、どう次の世代へ伝えていくのか――そこがすごく重要なテーマになっていると思います。
MC:歴史という言葉が出たので、吉田 羊さんの話に移りたいと思います。吉田さんが演じた悦子はとても重要な存在ですよね。過去と現在をつなぐ“架け橋”のようなキャラクターで、歴史的にも個人的にも強い意味を持っています。そんな複雑な役どころを演じるにあたって、原作小説や石川監督の脚本の中に、「このセリフ(あるいは瞬間)で自分の中にキャラクターが入ってきた」と思えるような手がかりはありましたか? たとえば「この一言で彼女の輪郭が見えた」と感じたような場面など。
吉田 羊:(英語で)吉田 羊と申します。悦子役を演じました。本日はお越しいただき、ありがとうございます。(日本語で)私が一番印象的だった悦子の台詞は、実は映画の中では使われていないのですが、「あの時は、景子も幸せだったのよ」というセリフです。脚本で読んだとき、とても印象に残りました。このセリフこそが彼女(悦子)の核ではないのかなと思っていました。ただ、その台詞の捉え方が、監督と私でニュアンスに違いがあって。でも今カミラが言ったように、自分の捉えていた台詞の感覚との違いの中にこそ、この悦子のキャラクターがあると思い、監督が意図するニュアンスのほうにすり合わせていきました。
MC:カズオ・イシグロさん、これまで多くの小説が映画化され、大きな成功を収められていますよね。作品によってはご自身が深く関わられたものもあれば、今回のように少し距離を置かれているものもあります(今回はエグゼクティブ・プロデューサーとして関わっていらっしゃいますが)。この小説はご自身にとって非常に特別で、作家として形成期に書かれた、個人的な意味を持つ作品だと思います。そんな作品を“他の誰かに委ねてもいい”と思えたのは、どんな瞬間だったのでしょうか? そして、石川監督のどんなところに信頼を感じたのですか? それがこの映画化を後押しした理由だったのでしょうか?
カズオ・イシグロ:いや、こんなことを言ったら一部の作家は気分を悪くするかもしれませんが……。
MC:だからこそ、あなたをお招きしたんです。(会場、笑い)
カズオ・イシグロ:彼らは原作に忠実な映画化を望みます。でも私は、忠実な映画化というものがあまり好きではないんです。それで、ほとんど最初の段階から――つまり、「ああ、彼(石川監督)はきちんとした映画人だ、信頼できる」と思った瞬間から――私は身を引こうと思いました。彼に会ったのは、ヴェネチア映画祭で彼の前作『ある男』(22)を観たあとでした。とても感銘を受けました。それで、私は作品を彼らに委ねたんです。というのも、私はこう思うんです。もし原作者がその映画の制作チームに積極的に関わっていないのなら、その創作の場は監督たちに委ねて、原作者は本当に一歩引くべきだと。もし尋ねられれば、私たちにも意見はあります。でも、そうでない限りは、それは(小説ではなく)映画として独立した作品にならなければならないと思うんです。石川監督を中心としたチームが語ろうとするものの一部にならなければならないんです。これは決して私の寛大さの表れではありません。ただ、私はこれまで本当にたくさんの映画を観てきました――そして、その中の95%くらいは、映画制作者が原作にあまりにも忠実であろうとしたためにうまくいっていないんです。時々思うんですよ――それって単に想像力の怠慢なんじゃないかって。「だって、もう全部そこ(原作)に書いてあるじゃないか」っていう発想ですね。だから私は、石川監督と彼のキャストに、この映画を本当に“自分たちのもの”として受け取り、まったく新しい場所へ持っていってほしかった。だから、ある段階で私は現場を離れました――そして、それができたことを本当にうれしく思っています。僕らはちょうどその前に、ビル・ナイと一緒に映画『生きる-LIVING』の仕事をしましたが、そのとき僕はまったく違う立場でした。あちらでは脚本家として関わっていたんです。時々、僕は脚本家としても仕事をしますが、やっぱりそれは小説を書くのとはまったく違うんですよね。そして、これは僕がよく感じていることなんですが、小説から映画を作るというのは、特に原作にある程度の名声がある場合、それは映画にとって非常に危険なことなんです。だからこそ、映画監督たちは自分たちのビジョンをしっかりと主張しなければならない。原作に引きずられるのではなく、素材を自分たちのものとして新しい形で語る必要があるんです。これは僕が謙遜して言っているわけではなく、むしろ劇作家的な発想なんです。僕はホメロスのようになりたいと思っていて――つまり、物語を書いたあと、それを他の人たちが自由に引き継ぎ、新しい形で語り継いでいく、そういう存在に。
MC:素晴らしいです。
カズオ・イシグロ:でも、それがまさに答えですよね。物語は世に出て、年月とともに人々がそれぞれの解釈や感情を持ち寄り、世代ごとに違う観客として受け取っていく。だからこそ、同じ物語でも、時代や観客によって少しずつ姿を変えていくんです。
MC:とても寛大な考えですね。これで、世界中の映画監督があなたと仕事をしたいと思うようになるでしょう。さて、ここはまさに“観客と作品を結びつける映画祭”でもありますので、ここからは会場の皆さんからの質問を受けたいと思います。マイクが用意されています。時間が限られていますので、なるべく簡潔に質問していただけると、より多くの方の質問をお受けできます。では……そちらの端の席の方、どうぞ。
観客:美しい映画でした。吉田 羊さんと監督に質問です。羊さん、通常は日本語で演技されているかと思いますが、今回はすべて英語での演技でした。英語での演技はいかがでしたか? また劇中で娘とのやり取りも英語になっていましたが、それによってコミュニケーションの感じ方に違いはありましたか? また、監督への質問です。とても文学的な作品を映像作品に翻訳するというのは、どんな作業でしたか?
吉田 羊:できるだけ英語で話してみますね。もちろん、日本語のセリフに比べて英語のセリフを覚えるのはとても大変でした。でも、この役を作るうえで一番大切だったのは、彼女が長崎からイギリスに移ってからの30年間の人生を想像することでした。つまり、言い換えると、私は彼女の人生――つまり、長崎から来て、娘の景子や過去の長崎での記憶、そして原爆のことをどう受け止めているのかを想像しました。劇中の娘ニキとの関係については、彼女(カミラ)がとても温かくて優しい人だったので、まったく難しさは感じませんでした。それに、彼女自身にも日本のルーツがあるので、私たちの関係を自然に築くことができたと思います。えっと、そんなところでしょうか(笑)。

Courtesy Vue Lumière
監督:たぶん次の質問にも英語でお答えしたほうがいいですね。今回の作品は“記憶”についての映画だと思っています。1950年代の長崎をどう描くかを考えたとき、私たちはたくさんのリサーチをしました。でも同時に、本当に描かなければならないのは「正確な再現」ではなく、「彼女がどう覚えているか」だったんです。そしてそれは、ある意味でカズオさん自身が覚えている長崎でもある。つまり、実際の長崎をそのまま再現することが目的ではなく、彼女の記憶の中の長崎――感情や想像の中の風景を描くことが重要だと気づいたんです。だから映像もより鮮やかで、生き生きとしたものにしたいと思いました。戦争が終わって7年後の長崎というと、人々はどうしても原爆の爪痕ばかりを想像します。でも実際には、すでに人々は前に進み始めていて、ファッションを楽しんだり、日常の喜びを取り戻していた。私たちは、そうした姿を描きたかったんです。そして、それは1950年代の日本映画ではほとんど描かれなかった部分でもあります。だからこそ、それがこの作品づくりの大きなコンセプトのひとつになりました。

Courtesy Vue Lumière
MC:さて、残念ながらお時間となってしまいました。それでは、改めてこの素晴らしい皆さんに、盛大な拍手をお送りください! ありがとうございました。
公開表記
配給:ギャガ
絶賛公開中
(オフィシャル素材提供)