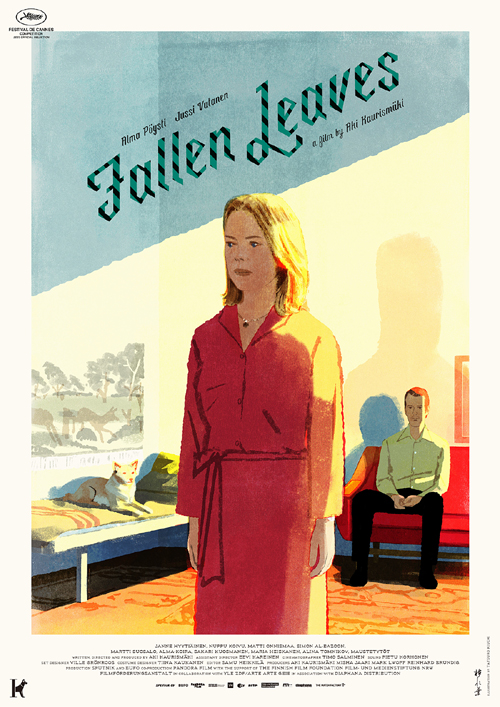フランスで絶賛された青春映画『Winter boy』が12月8日(金)より日本全国にて順次公開開始。そこで公開を記念して、本編映像第三弾ならびに監督のオフィシャル・インタビューが初解禁となった。
父の死、そして、はじめてのパリへ。
年上の青年との出会いが、少年を光へと導くが……。
今回解禁となる本編映像第三弾は、恋の喜びとパリの朝焼けを描いた本作屈指の美しいシーン。父を亡くし塞ぎ込む弟・リュカを心配した兄・カンタンが、気分転換にと自身の暮らすパリに一週間だけ招く。そこでリュカは兄の同居人で兄と同じ美大出身のリリオに恋をする――。
映像は、パリで印象に残っている出来事を独白するリュカから始まる。想いを寄せる彼の傍で寝たいと、ささやかな言い訳を用意してこっそりとリリオの部屋で眠るリュカ。近いようで遠い、数センチの距離だ。目を覚ますと、リリオはランニングの準備をして誘われる。日本でも大ヒットしたシルヴィ・ヴァルタンの「あなたのとりこ」がバックに流れるなか、朝焼けのパリの街並みを憧れの男性と走り抜けてゆく本作屈指の名シーン。クリストフ・オノレ監督の自伝的物語である本作を監督は『この映画の主題は「悲劇の中に、喜びを見つけること」』と語る通り、「あなたのとりこ」の歌詞“涙のあとには喜び 冬が過ぎれば花の季節 すべて終わったと思えても 最後は愛が勝つ”が、胸に響く。
26歳で作家デビューし、自身のセクシュアリティをオープンに表現し続けるクリストフ・オノレ。
自分自身で亡くなった父親役を演じた本作は「愛を願う映画」。自伝的な映画『Winter boy』を語る――。
「カイエ・デュ・シネマ」に映画評を寄稿し、その後映画監督となり、舞台の演出なども手掛ける多才なクリストフ・オノレ。自身のセクシャリティやパーソナリティを強い信念のもと真正面から表現し、観る者に勇気を与え続けている。本作はオノレの少年時代を描いた自伝的な物語。愛する者の死に直面したとき、その苦しみをどう乗り越えていけばいいのか――どんな絶望の底にも差し込む希望の陽に、優しく心身を温められる感動作だ。
この度、初解禁となるクリストフ・オノレ監督のオフィシャル・インタビューでは、本作を主人公リュカのラブ・ストーリーであることを認めつつ、だが「メロドラマではなく、愛を願う映画なのだ」と語る。また、父を突然亡くすという痛ましい記憶を甦らせることについては「日常生活が崩壊したとき、そこには語られるような物語やストーリー展開もない。混乱した気持ちと、もう何もかもが意味をなさず、翻弄されているような印象しかない」と、その作劇の難しさを吐露。だからこそ「当時の気持ちに忠実であろうと最善を尽くした」と語る。そんな日々の中で「あたかも現在のときの中で感情を追体験しているような」感覚を得て、「自分の過去にタイムスリップしたというより、過去の感覚を今の現実に投影したもの」になったと、本作の魅力を語った。
自分自身で亡くなった父親の役を演じたことについては「私の声や目、動きのなかに、父がまだ何らかの形で存在していると思い、父の亡霊と化した」と表現。さらに、今回はじめての仕事となったジュリエット・ビノシュについては「ジュリエットのおかげで映画の力を信じられるのです。撮影現場で彼女と仕事をすることで、創作の可能性が新たな領域まで広がる」と大絶賛だ。
映画『Winter boy』クリストフ・オノレ監督インタビュー
いつ撮影したのですか?
クランクインは2021年の末頃です。21年の冬は、私たちにとっても特異な時期でした。というのも選挙期間中、しかもパンデミックが蔓延していた数ヵ月後ということもあり、撮影現場での作業に大きな支障をきたしたからです。ウクライナ戦争の勃発も目前に、とても敏感な時期でもありました。でもそれゆえに本作は、この特別な時代の証人となれたか、少なくともその痕跡を残せたと感じています。この作品は内なる緊張感によって、崩壊の予感を煽る。動じることなく、あきらめの衝動に屈せず最善を尽くすだけ。おそらくこの映画の主題は「悲劇の中に、喜びを見つける」ということなのです。だからこそ、この映画は何よりもまずラブ・ストーリーではありますが、メロドラマではなく、愛を願う映画なのだと思います。
お父様はあなたがまだ十代の頃に亡くなりました。すでに小説や最新の舞台「Le Ciel de Nantes(原題)」でお父様の死を扱っていますが、 本作ではこれまでになくオープンに語っていますね。
私の映画はしばしば失脚や不可逆性、限界について扱ってきましたが、父の死後数ヵ月間の特別な状態についての映画を撮る日が来るとは思ってもみませんでした。『ソーリー・エンジェル』(18)以降、私は新しいプロジェクトのひとつひとつに真摯に取り組もうと努力してきました。基本的に人々が映画を作るのは、心の奥底で誰かを恋しく思ったり、残酷なまでにあるいは漠然と、映画で空虚感を埋めようとするからだと思います。だからあのとき、私はより強く父を恋しく思っていたのかもしれません。
悲惨で痛ましい感情を浮き彫りにしていますが、それを甦らせる作業は苦痛を伴いましたか?
かなり体力を消耗しました。というのも、この感情が精神の崩壊を引き起こし、現在もその影響が続いているからです。しかし私は、悲しみを操作したり、なぐさめの光を当てようとしたりはしませんでした。それどころか、あの頃ティーンエイジャーだった私と当時の気持ちに忠実であろうと最善を尽くしたのです。心地よい時間の経過ではなく、むしろ脚本と演出を駆使して、あの混沌とした圧倒的で予測不可能な本質を再現し、自分が感じた感情に忠実であり続けたかった。悲劇に見舞われ、日常生活が崩壊したとき、そこには語られるような物語やストーリー展開もない。混乱した気持ちと、もう何もかもが意味をなさず、翻弄されているような印象しかない。このような感情にできるだけ近づこうとする姿勢は、あたかも現在のときの中で感情を追体験しているようで、そこから架空の登場人物を生み出すことができました。私にとってリュカは、彼の在り方そのものにより、今や架空の人物となりました。かつての自分の記憶というよりも、現代のある一人の若者として見る。彼は私の過去の記憶と、今日の世界についての注意深い洞察の両方を兼ね備えています。だからこの映画は、自分の過去にタイムスリップしたというより、過去の感覚を今の現実に投影したものと言えます。
作品ではご自身が父親役を演じることで、死者の立場になっていますね。
私は役者ではないし、演じるのは気恥ずかしいです。でも今回だけは、恥ずかしさを克服して作品の一部になれ、うれしかった。自分自身を父の「投影」として描きました。私の声や目、動きのなかに、父がまだ何らかの形で存在していると思い、父の亡霊と化した。こういう形而上学的な話は、私の故郷であるブルターニュ地方ではよくある考えなのです。しかもバカバカしいと思う人もいるかもしれないが、私は生者のほうが死者の亡霊だと思っています。死者に憑いているのは私たちであって、その逆ではないんじゃないかと。それはポールにとっても重要なことでした。俳優と監督の関係において、私は彼の父親代わりになる必要があった。そうすることで、彼は息子役になりきることができるからです。撮影の最初の2日間、一緒にシーンを演じ、私たちはお互いをよく知らなかったのですが、気がついたら2人で車の中にいました。私は自分が俳優として何をしているのか手探りの状態でしたが、その無能さが、私たちの間に唯一無二の関係を築かせたのです。私たちは打ち解け、愛情は限りないエネルギー、喜び、信頼の源となりました。結果的にそれがポールへの演技指導となったわけです。いわば私がハンドルを握り、方向を示して見守りながらも、必要であれば道から離れるといった感じです。
ジュリエット・ビノシュと仕事をするのは初めてでした。
長年夢見てきたことでした。以前、あるプロジェクトでジュリエットに出演を打診したのですが断られてしまった。女優の多くは、一度 「ノー」と言ったら二度と打診されないと思ってる。確かに時々そんなこともある。しかし、断られたことを飲み込んで、再びオファーしたいという意欲がさらに高まることもあります。ジュリエットがイザベルという役に「イエス」と言ってくれてよかった。彼女はこの映画に欠かせない人間味と深みをもたらしてくれました。彼女の演技の力強さや、全編にわたり感じさせてくれる映画への情熱には本当に感銘を受けました。カトリーヌ・ドヌーヴやイザベル・ユペールのように、人々に再び希望を与えるような役者なのです。それに彼女は映画を作ることにとても熱心だから、彼女のために映画を作りたいと思うようになります。ジュリエットのおかげで映画の力を信じられるのです。撮影現場で彼女と仕事をすることで、創作の可能性が新たな領域まで広がる。それに彼女は素晴らしい共犯者のようです。彼女は限られた人間と密かに、まるで陰謀のように映画作りをするのを楽しんでいます。秘密の人脈というか、集団に属して団結し奮闘して、新しい映画を誕生させたいという強い意志がある。こうした撮影現場での一体感は、本当に楽しく貴重なものです。私は、映画の最後は母親に焦点を当てなければならないと考えていました。リュカの声を引き継いで、彼女に物語を語ってほしかった。彼女は、完全なハッピーエンドとは言えないかもしれないが、少なくとも明るく、甘く、温かいエンディングを飾る役目を請け負ってくれた。ジュリエットはこの哲学的選択を完全に理解し、それを繊細かつ力強く体現してくれた。ジュリエットを撮影することは、まるで生命が常に脈打っていると感じさせる、血液がドクドクと流れる血管を撮影するようなものです。

公開表記
配給:セテラ・インターナショナル
12月8日(金)よりシネスイッチ銀座、新宿武蔵野館ほか全国順次公開
(オフィシャル素材提供)